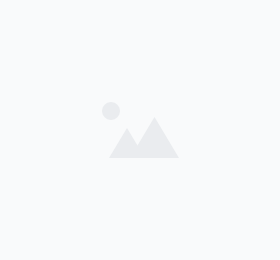CN比とイチゴ土壌管理
CN比 イチゴ土壌と堆肥有機物の基礎
CN比は「全炭素量÷全窒素量」で表される指標で、堆肥や土壌中の有機物がどれくらいの速度で分解し、どの程度の期間土壌中に炭素が残るかを判断する目安になります。 例えば同じ量の堆肥でも、CN比が低いと分解が早く短期的な肥料効果が大きくなり、CN比が高いと分解が遅く長期的な土づくり効果が大きくなると整理されています。
イチゴの有機栽培事例では、約50点の土壌を調査したところ、全炭素/全窒素比が10程度の圃場が多く、想像よりも炭素が少ない土壌が多いという報告があります。 この結果から、炭素を増やしたいからといって高CN比堆肥をむやみに多量投入するのではなく、現状のCN比を把握してから投入量と資材の種類を決めることが重要とされています。
参考)いちごの有機栽培について教えてください。 – ペ…
多くの県の施肥・土づくり指針では、有機物や緑肥の炭素率(C/N比)が20〜30を境に分解パターンが変わると説明され、これを踏まえて施肥量の目安を示しています。 一般的には、C/N比が20未満の有機物は分解が速く窒素が短期間で無機化しやすく、20〜30程度では適度な肥効と土壌有機物の蓄積が両立し、30を超えると分解が遅く土づくり効果は高い一方で初期の窒素不足リスクが高まると整理されています。
参考)https://www.pref.chiba.lg.jp/annou/documents/3103sehikijun_4kankyou.pdf
イチゴ土壌に使われる牛ふん堆肥やバーク堆肥は、製品によってC/N比が18〜21前後のものが多く、窒素供給と有機物蓄積の両方を狙える中庸タイプとして位置付けられています。 一方で、米ぬかや油かす主体の堆肥はC/N比が比較的低く肥料的な働きが強いため、イチゴの基肥や追肥に組み合わせると窒素過多になりやすく、量や時期の調整が必要とされています。
参考)https://www.naro.go.jp/laboratory/karc/prefectural_results/files/30_5_03.pdf
イチゴ土壌と有機物の関係を整理するうえで、以下のようなイメージを持つと管理しやすくなります。
- 🌱 CN比が低い有機物(例:20未満)は「肥料寄り」で、速効性の窒素供給が主な役割。
- 🌱 CN比が中庸(20前後)は「肥料+土づくり」の両方をねらえるバランス型。
- 🌱 CN比が高い有機物(30以上)は「土づくり寄り」で、初期は窒素飢餓リスクがある一方、長期的な腐植蓄積に有利。
| 有機物のCN比 | 主な特徴 | イチゴ栽培での注意点 |
|---|---|---|
| おおよそ15未満 | 分解が速く、短期間で窒素が放出されやすい。 | 苗のチッソ過多や軟弱徒長を招きやすいので、基肥量と追肥時期を慎重に設計する。 |
| 15〜25程度 | 適度な速度で分解し、肥料効果と土壌有機物の蓄積を両立しやすい。 | イチゴの長期栽培に向いた「ベース」として使いやすく、連作圃場の地力維持にも役立つ。 |
| 25以上 | 分解が遅く、初期は土壌中の窒素を微生物が抱え込むため窒素飢餓を起こしやすい。 | 定植前に多量施用する場合は、別途窒素肥料を組み合わせるか、施用時期を早めて分解期間を確保する。 |
CN比 イチゴ苗質と炭素率と光合成
CN比は土壌だけでなく、苗や成株の体内にも存在し、地上部のC/N比が生育型や処理の効き方に影響することが報告されています。 イチゴ「あまおう」の苗を対象にした研究では、地上部のC/N比が高い苗ほど低温暗黒処理の有効率が高く、処理後の花芽分化や生育が安定する傾向が示唆されています。
また、イチゴの窒素形態(硝酸態窒素とアンモニア態窒素の比率)や施用濃度を変えた試験では、窒素レベルが高すぎたりアンモニア態の割合が高いと、根のカリウム含有率が上がる一方で地上部のC/N比が低下し、栄養成長に偏った状態になることが示されています。 これは、窒素が過剰な環境では炭水化物より窒素含有成分の割合が増え、葉が軟弱で病害に弱い体質になりやすいことを裏付けています。
参考)https://youeki.jp/hydro_backNO/pdf/13-1_042.pdf
光合成と着果負担量を同一の時間軸で追跡した研究では、イチゴの光合成量が安定して高い株ほど乾物生産量と収量が高く、CO₂施用や適切な光条件で葉光合成を高めると収量が向上することが示されています。 苗の段階で葉面積と葉肉の厚みが十分で、かつ無駄な徒長が少ない苗は、光合成能力とC/N比のバランスが取れていると評価されやすく、定植後の根張りと花芽分化も安定しやすいと考えられます。
参考)【公式】いちごの栽培ガイド:効果的な肥料と農業資材の選定方法
現場で苗質とCN比をリンクさせて考える際には、以下のポイントを意識すると整理しやすくなります。
参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/hrj/21/2/21_205/_pdf
- 🍓 肥培管理を強めすぎて葉色が濃く柔らかい苗は、体内C/N比が低下しているサインと考え、窒素施肥や液肥濃度を見直す。
- 🍓 葉が厚く、節間が締まりつつも極端な窒素制限をしていない苗は、光合成量とC/N比のバランスが良く、処理への反応も安定しやすい。
- 🍓 苗づくりの終盤で急に窒素を切るのではなく、育苗期間を通じてやや控えめな窒素管理を続けることで、過度な低C/N比化を防ぐ。
特に四季成り性品種や長期どり作型では、栄養成長から生殖成長への切り替えをスムーズにするため、苗の時点から「肥えさせ過ぎない」ことが重要とされ、これは体内C/N比を適度に高めておくイメージに近い管理になります。 苗質のチェックシートに、葉色や草姿だけでなく「肥料切り時期」「窒素施肥量の推移」といったCN比に関わる指標を組み込んでおくと、後から問題の原因を振り返りやすくなります。
参考)https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/ktebiki1.pdf
CN比 イチゴ収量と施肥設計と基肥追肥
イチゴの施肥基準は県ごとに異なりますが、土耕栽培の代表的な事例として、栃木県の「とちおとめ」では10aあたり窒素で基肥15kg、追肥5kgなど、N・P・Kの標準施肥量が示されています。 一方で、同じ栃木県内の高収量農家の事例では、窒素をやや少なめにして有機質肥料やもみ殻堆肥、ケイ酸カリなどを組み合わせ、CN比を意識した施肥体系で単収7t超を上げた報告もあります。
福岡県の「あまおう」の畝連続利用栽培の試験では、杉皮バーク堆肥(C/N比21)を10aあたり2t施用しつつ、基肥窒素量を3〜4.5kg/10a程度まで減らしても、全面耕起栽培と同等以上の収量と果実品質が得られたとされています。 この試験から、C/N比が中庸の堆肥を組み合わせることで、無理に窒素量を増やさなくても地力と収量を両立できる可能性が示されています。
一方、多くの施肥指針では、C/N比の高い有機物を定植前に多量に鋤き込むと、分解の初期に土壌中の無機態窒素が微生物に取り込まれて作物が利用できる窒素が一時的に不足する「窒素飢餓」が起こると注意喚起しています。 その対策として、C/N比20以下となるよう別途窒素肥料を追肥したり、分解が進んだ堆肥を使うことが推奨されており、イチゴでも同様の配慮が必要です。
参考)https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/319444.pdf
イチゴの収量とCN比を結びつけて施肥設計を考えるとき、現場レベルでは次のような組み立てが有効です。
参考)https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/02060107sakumotu1.pdf
- ⚖️ 土壌診断で全炭素・全窒素を測定し、圃場ごとのCN比と有機物水準を把握したうえで、基肥量を調整する。
- ⚖️ C/N比20前後の堆肥を基礎として、必要に応じて低C/N比の有機質肥料や化学肥料で窒素を上乗せし、初期生育の安定を図る。
- ⚖️ 追肥は液肥中心とし、花房数や葉色、ランナー発生状況を見ながら小刻みに与えることで、株の体内C/N比が急激に変動しないようにする。
- ⚖️ 連作年数が進んだ圃場では、CN比の高い緑肥や堆肥で土づくりを行いつつ、窒素肥料は緑肥のC/N比を踏まえた利用率を前提に計算する。
特に長期作型や高設栽培では、培地や土壌中の有機物が年々蓄積し、CN比の変化が肥効や水分保持性に影響してきます。 連作障害対策としても、単に「堆肥を入れる」ではなく、「どのC/N比の有機物をどれだけ、何年続けるか」という視点で施肥設計を記録しておくことが、後々のトラブルシューティングや技術継承に役立ちます。
参考)https://www.farc.pref.fukuoka.jp/farc/seika/h17b/06-12.pdf
CN比と有機物分解、施肥設計の考え方を体系的に確認したい場合に役立つ農林水産省の資料です。
作物別施肥基準(農林水産省)
CN比 イチゴ有機栽培と土壌微生物と緑肥
有機栽培のイチゴでは、堆肥や緑肥の施用で土壌微生物を活性化させ、物理性や病害抑制力を高めることが重視されますが、その際の鍵のひとつが有機物のC/N比です。 緑肥の種類によってC/N比は大きく異なり、マメ科はC/N比が低く分解が早い一方、イネ科はC/N比が20〜50と高く分解が遅く、有機物を長く土壌に残す効果が大きいとされています。
長崎県などの試験では、複数の緑肥を土壌に埋設して窒素と炭素の分解率を追跡し、C/N比の違いが窒素の無機化パターンに大きく影響することが示されています。 C/N比の高い緑肥では分解初期に窒素が微生物に取り込まれ、のちにゆっくり放出されるため、イチゴの定植時期とのタイミングを合わせることが収量安定に重要です。
参考)https://www.pref.nagasaki.lg.jp/e-nourin/nougi/theme/theme/brPDF/business_report_2015/H27-06.5_kenkyugaiyou-kankyou.pdf
太陽熱養生処理をイチゴ圃場で実施している事例では、土壌の団粒化促進や病害虫密度の低減と並んで、「C/N比調整と炭素源補給」が目的として挙げられています。 有機物を鋤き込んだあとにマルチで被覆して太陽熱処理を行うと、分解が進み窒素飢餓のリスクが軽減されると同時に、病原菌や線虫の密度も低下しやすいとされます。
参考)太陽熱養生処理
さらに近年は、窒素固定やリン酸溶解などの機能を持つ土壌微生物を利用したバイオ肥料の研究が進み、化学肥料削減と収量維持を両立させる技術として注目されています。 これらの微生物資材は、土壌中の窒素循環を助けて作物が利用しやすい形に変換する役割を担い、C/N比の影響を受けつつも、持続的な栄養供給と病害抑制に寄与する可能性が示されています。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8724949/
イチゴの有機栽培でCN比と土壌微生物・緑肥を活かすための実務的なポイントを整理すると、次のようになります。
- 🌱 イネ科の高C/N比緑肥で「土づくり」と炭素ストックを狙い、定植より十分前に鋤き込んで窒素飢餓リスクを下げる。
- 🌱 マメ科緑肥や低C/N比の堆肥を、イチゴの初期生育を支える「肥料寄り資材」として位置づけ、過剰施用を避ける。
- 🌱 太陽熱養生処理やバイオ肥料を組み合わせ、CN比に応じて微生物相を整えることで、連作圃場の病害リスクを抑えつつ地力を維持する。
CN比 イチゴ炭素貯蔵と環境配慮型経営
農地土壌の有機物管理は、作物の収量だけでなく、地力維持と地球温暖化の緩和の両面で注目されており、その中心的な指標がC/N比です。 有機物のC/N比が大きいほど分解が遅く、難分解性成分を多く含む資材は土壌中に長く残って炭素を貯蔵する効果が高いことが知られています。
環境配慮型農業のガイドラインでは、環境負荷を軽減するために、炭素と窒素のバランスが取れたC/N比10〜15程度の有機質肥料を基本としつつ、化学肥料の削減や窒素の流亡抑制を図ることが推奨されています。 こうした指針はイチゴにも適用でき、特に高設栽培やハウス栽培で排水やガスの環境負荷が問題になりやすい場合、CN比を意識した有機物管理はエコファーマー認定などとも親和性が高いと考えられます。
参考)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/chikikigyo/files/greenkehshukaitorikumijirei.pdf
市販の植物性完熟堆肥の中には、有機炭素13〜14%、全窒素0.7%前後でC/N比18〜19と表示される製品があり、比較的低いC/N比で肥料効果と土づくり効果を両立しやすい設計になっています。 こうした堆肥を数年連用することで、極端な高C/N比資材を使わなくても土壌有機物含量が少しずつ増加し、団粒構造や保水性の改善による栽培安定化が期待できます。
参考)スーパー緑の堆肥®1号
さらに、食品廃棄物を水熱分解してイチゴ培土に利用する研究では、原料や処理条件によってC/N比を調整しつつ培土組成を検討する試みが行われています。 これにより、廃棄物由来の有機物を資源として循環利用しながら、イチゴ栽培に適したCN比と物理性を持つ培養土を設計する可能性が示されており、カーボンニュートラルや食品ロス削減の観点からも注目されます。
参考)https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010927339.pdf
イチゴ農家がCN比を環境配慮型経営のツールとして活用する際の具体的なアクション例は次の通りです。
参考)https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/272625/zizokunougyou.pdf
- 🌎 圃場ごとに有機物投入量と推定C/N比を記録し、年度ごとの土壌炭素ストックの変化を簡易的に見える化する。
- 🌎 施肥設計書や出荷団体への報告資料に、「有機物のC/N比」「窒素施肥削減率」などの指標を追記し、環境配慮の取組として打ち出す。
- 🌎 緑肥や堆肥の選定時に「C/N比」「原料由来」「炭素貯蔵への寄与」をチェックポイントに加え、単なるコスト計算だけでなく中長期的な地力とブランド価値を評価する。
土壌有機物とC/N比が農業生産や地力・環境にどう関わるかを俯瞰的に理解するのに役立つ総説です。
土壌有機物と農業生産との関係についての総説(J-Stage)