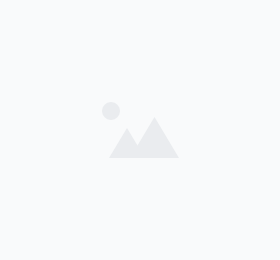クラウンの冷却の重要性
クラウンの冷却といちごの花芽分化促進のメカニズム
いちご栽培、特に促成栽培において、生産者の頭を最も悩ませるのは「花芽分化」のタイミングとその安定性です。近年、温暖化の影響で秋季の気温が下がらず、定植後の花芽分化が遅れる事例が多発しています。ここで決定的な役割を果たすのが「クラウンの冷却」です。いちごの生長点(クラウン内部)は、温度を感知するセンサーのような役割を果たしており、この部分の温度感受性が植物全体の生理反応を支配しています。
通常、いちごは短日・低温条件で花芽を分化しますが、気温が25℃を超えるような環境下では、体内の窒素レベルが適切でも花芽分化が抑制され、栄養成長(葉やランナーの発生)が優先されてしまいます。しかし、興味深いことに、葉や根が暖かい環境にあっても、「成長点であるクラウン部のみ」が低温(特に20℃±2℃の範囲)を感じていれば、植物体は「冬が近づいている」と錯覚し、生殖成長(花芽の形成)へとスイッチを切り替えることが研究により明らかになっています。これが局所冷却技術の根本的なメカニズムです。
この技術の最大のメリットは、第1次腋花房(2番果)以降の分化を強力に促進する点にあります。頂花房(1番果)の分化は育苗期の管理で決定されますが、定植後の高温で遅れがちなのが第1次腋花房です。ここが遅れると、いわゆる「収穫の中休み」が発生し、単価の高い1月~2月の出荷量が激減してしまいます。クラウンを物理的に冷却し、強制的に花芽分化シグナルを送り続けることで、この中休みを短縮、あるいは消失させ、連続的な収穫を可能にします。生理学的には、クラウン部の温度低下がオーキシンやジベレリンといったホルモンバランスを変化させ、フロリゲン(花成ホルモン)の活性化を促していると考えられます。
参考リンク:農研機構(九州沖縄農業研究センター)の研究成果によると、クラウン温度を20℃前後に制御することで、第1次腋果房の分化が早まり、年内および2月までの早期収量が増加することが実証されています。
クラウンの冷却の具体的な装置と循環システムの導入
クラウンの冷却を実践するためには、専用の装置と循環システムの構築が不可欠です。基本的には、冷却水を循環させるチラー(冷却水生成装置)、送水ポンプ、そして株元に設置する熱交換用のチューブで構成されます。このシステム導入において最も重要なのは、「熱交換効率」と「ランニングコスト」のバランスです。
まず、株元に設置するチューブの選定が重要です。一般的には、熱伝導率の良いポリエチレン製や架橋ポリエチレン管、あるいは専用の柔らかい樹脂製チューブが用いられます。このチューブをクラウン(株元)に直接接触させるように這わせ、内部に冷水を流します。チューブの径が太すぎると作業の邪魔になり、細すぎると熱交換容量が不足するため、外径10mm~15mm程度のものが主流です。チューブ内を流れる水の温度は、クラウン表面温度を20℃目標にする場合、熱ロスを考慮して15℃~17℃程度に設定するのが一般的です。
冷却源としては、以下の2つのパターンが多く採用されています。
- ヒートポンプチラー方式: 電気を使って強制的に水を冷却する方式です。温度制御が正確で、安定した効果が期待できます。近年のヒートポンプは省エネ性能が高く、ハウス全体を冷房するコストに比べれば数分の一で済みますが、初期導入コストは数十万円〜百万円単位とかかります。
- 地下水利用方式: 豊富な地下水がある地域で有効な、極めて低コストな手法です。年間を通じて15℃前後の水温が安定している井戸水があれば、それを汲み上げてチューブに流すだけで冷却効果が得られます。チラーの電気代がかからないため、経営的なメリットは計り知れません。ただし、使い終わった水の排水処理や、水温がやや高めの地域では冷却能力不足になるリスクを考慮する必要があります。
導入の際は、配管の結露対策も考慮する必要があります。冷たい水が流れる配管は、高湿度のハウス内では激しく結露します。これが通路や培地を過剰に濡らし、病害の原因になることがあるため、断熱材を巻くか、結露水を受けるドレインの設置が推奨されます。
参考リンク:宮城県の農業現場における技術資料では、地下水を利用したクラウン冷却システムが、エネルギー消費を大幅に抑えつつ夏秋いちごの品質向上に寄与する事例が紹介されています。
クラウンの冷却と高温期の栽培管理のポイント
クラウンの冷却を行う高温期(9月~10月、あるいは夏秋栽培の夏場)は、いちごにとって最もストレスがかかる時期です。この時期の栽培管理において、クラウン冷却は単なる「冷やす」作業以上の意味を持ちます。それは、高温障害による株疲れを回避し、根の活力を維持するための防衛策でもあります。
高温期には、日中のハウス内気温が30℃を超えることも珍しくありません。この環境下でクラウン冷却を行う場合、以下の管理ポイントが重要になります。
- 処理開始のタイミング: 定植直後から開始するのが鉄則です。活着(根付くこと)が確認でき次第、あるいは定植と同時に冷却を開始します。遅れると、高温による消耗が先行し、冷却効果が出る前に花芽分化のチャンスを逃してしまいます。
- 日中と夜間の使い分け: 24時間連続冷却が最も効果的ですが、コスト削減のために「夜間のみ」あるいは「日中のみ」にするという議論があります。研究によると、「日中の高温ストレス緩和」と「夜間の呼吸消耗抑制」の両方が重要です。特に夜温が下がりにくい熱帯夜が続く場合は、夜間の冷却(クラウン部だけでも20℃以下にする)が、呼吸による炭水化物の無駄な消費を抑えるために極めて有効です。
- 遮光との併用: クラウン冷却を行っているからといって、強烈な直射日光を放置してよいわけではありません。葉温が上がりすぎると気孔が閉じ、光合成が止まります。適度な遮光(30%〜50%)と換気を組み合わせ、葉の温度を制御しつつ、クラウンを局所冷却する「合わせ技」が、最強の生育環境を作り出します。
また、高温期の灌水管理とも密接に関係します。クラウン冷却をしていると、株元の地温が下がるため、根の吸水活性が維持されます。通常なら暑さで根がバテて吸水力が落ち、萎れが出る場面でも、冷却株は元気に水を吸い上げます。そのため、灌水量は通常よりも多めに設定する必要が出てくる場合があります。ここを見誤ると、せっかく代謝が良いのに水不足で光合成できないという本末転倒な事態になりかねません。
クラウンの冷却の失敗しない温度管理と注意点
クラウンの冷却は魔法の技術のように思えますが、現場での失敗例も少なくありません。その多くは「温度管理の不徹底」と「物理的な設置ミス」に起因します。導入したのに効果が出ない、逆に生育が悪くなったという事態を避けるために、以下の落とし穴に注意する必要があります。
1. 冷却温度の下げすぎによる矮化(わいか)
「冷やせば冷やすほど良い」というのは大きな間違いです。クラウン部の温度が10℃〜13℃を下回るような過剰冷却を続けると、いちごは「冬眠」モードに入ろうとしてしまい、葉の展開速度が極端に遅くなる(矮化する)現象が起きます。特に、地下水が非常に冷たい地域や、チラーの設定を下げすぎた場合に発生します。あくまで目標は「花芽分化に最適な20℃前後」であり、休眠打破のための5℃ではありません。センサーを用いて、チューブ表面温度ではなく「クラウンの実温度」や「近接する培地温度」をモニタリングすることが不可欠です。
2. チューブの接触不良(これが最も多い失敗)
いちごは生き物であり、成長に伴ってクラウンの太さや位置が変化します。定植時にはぴったりとチューブを当てていても、葉が増えたり、クラウンが上に伸び上がったりすることで、チューブとクラウンの間に隙間ができることがあります。空気が断熱材となり、冷却効果がクラウンに伝わらなくなります。週に一度は見回りを行い、チューブの位置を微調整する、あるいはチューブを軽く押し当てるための留め具を工夫するなど、物理的なメンテナンスが効果を左右します。
3. 結露による病害(炭疽病・灰色かび病)
冷却チューブの表面は常に結露しています。この水滴がクラウンや葉柄に常時接触している状態は、菌にとって天国です。特に高温多湿時の炭疽病は致命的です。対策としては、チューブに透湿性の低いカバーを巻く、あるいは株元に直接水滴がたまらないようにマルチの張り方を工夫するなどの対策が必要です。また、循環水の設定温度を、露点温度ギリギリを見極めて調整する(例えば15℃ではなく18℃にする)といった高度な管理も、病害リスクを下げるために有効です。
参考リンク:埼玉県農業技術研究センターの報告では、親株のクラウン冷却における花芽分化促進効果と、年次による変動要因(気温や管理方法の違い)について詳細なデータが示されています。
クラウンの冷却と光合成促進を両立する生理学的メリット
ここまでは一般的な冷却効果について解説してきましたが、クラウン冷却には、あまり語られることのない「株全体の生理バランスの最適化」という独自の大きなメリットがあります。これは、従来の「夜冷育苗」や「株冷(冷蔵庫に入れる処理)」とは決定的に異なる点です。
従来の短日夜冷処理は、株全体を低温環境(暗黒低温)に置くため、花芽分化は強力に促進されるものの、その間、植物体の代謝は低下し、光合成産物の蓄積よりも呼吸抑制が主眼となります。その結果、花芽はできても株自体が小さくなったり、定植後の馬力が不足したりすることがありました。
一方、クラウンの局所冷却は、「頭寒足熱」ならぬ「頭熱芯寒」の状態を作り出します。
- 葉(ソース器官): ハウス内の温暖な気温と十分な日射を受け、気孔を全開にして高い速度で光合成を行います。温度が高いため酵素活性も高く、糖分をガンガン生産します。
- クラウン(シンク器官・司令塔): 冷却により20℃前後に保たれているため、「今は涼しい秋だ」と判断して花芽分化の指令を出しつつ、呼吸によるエネルギーロス(消耗)を最小限に抑えます。
この「高い光合成速度(葉)」と「低い呼吸消耗&花芽分化シグナル(クラウン)」の分離こそが、クラウン冷却の真髄です。
さらに近年注目されているのが、高濃度CO2施用との組み合わせです。通常、CO2施用を行うためにハウスを締め切ると気温が上昇し、花芽分化が止まってしまうジレンマがありました。しかし、クラウン冷却があれば、ハウス内気温が30℃近くになってもクラウンは20℃を守れるため、「高濃度CO2環境下で光合成を最大化させながら、花芽もしっかり作る」という、かつては不可能だった栽培環境を実現できるのです。
これは単なる開花調節技術にとどまらず、収量(バイオマス)の最大化を目指す現代の環境制御農業(スマート農業)において、極めて合理的かつ先進的なアプローチと言えるでしょう。この生理学的メカニズムを理解して導入することで、単に「花が早く来る」だけでなく、「圧倒的に太い花が、樹勢を落とさずに連続して来る」という最高の結果を得ることが可能になります。

エムリットフィルター D-070_210 / トヨタ クラウン S21# / レクサス GS L1# IS E3# RC C10 / 87139-30110 / 87139-30100-79 エアコンフィルター