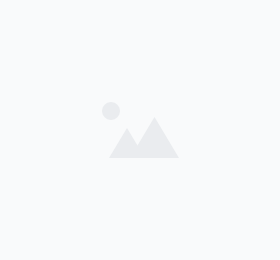イチゴの定植の遅れの影響
イチゴの栽培において、定植のタイミングは作型全体の成否を左右する極めて重要な分岐点です。一般的に、イチゴの定植が適期よりも遅れてしまった場合、生産者が最も懸念すべき「イチゴの定植の遅れの影響」は、単に作業が後ろ倒しになることだけではありません。植物生理学的な視点から見ると、地下部の根の伸長と地上部の葉の展開のバランス、いわゆるT/R比(地上部重/地下部重比)の形成に重大な支障をきたすリスクが高まります。
具体的には、定植が遅れることで、本格的な寒さが到来する休眠期までに十分な根群域(ルートゾーン)を確保できなくなります。イチゴは気温が低下すると生育が緩慢になり、やがて矮化(ロゼット化)して休眠状態に入ります。この休眠に入る前の「秋の貯金」とも言える期間に、どれだけクラウン(短縮茎)を肥大させ、太く充実した一次根を地中深くに張らせることができるかが、厳寒期の草勢維持と春以降の収量爆発力を決定づけます。
参考)イチゴ苗の植え付けが遅れてしまいました。植え付け後にしておい…
定植が遅れると、この根張りの期間が物理的に短縮されます。結果として、株が貧弱なまま花芽の発達を迎えることになり、頂果房(一番果)の果実肥大に必要な養分を根から十分に吸い上げることができず、果実が小玉傾向になったり、極端な場合は株疲れを起こして「なり疲れ」の状態に陥ったりします。さらに、根の張りが浅い株は、厳寒期の低温や乾燥といった環境ストレスに対する耐性が著しく低下するため、冬場の管理が難しくなるという悪循環を生み出します。
参考)https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/kikoguide/documents/20240606102211.pdf
しかし、近年の気候変動、特に9月の記録的な残暑を考慮すると、「定植遅れ」は必ずしもネガティブな側面ばかりではありません。高地温による根腐れや炭疽病などの土壌伝染性病害のリスクを回避するために、戦略的に定植時期を遅らせるという判断も、現代の農業現場では重要な選択肢の一つとなりつつあります。重要なのは、遅れたことによるデメリットを正確に理解し、それを補うための栽培管理技術(リカバリーショット)を適切に講じることです。
定植後の初期管理におけるリカバリーに関する参考情報。
定植が遅れた場合のリカバリー方法とリン酸肥料の活用について(タキイ種苗)
イチゴの定植の時期が遅れると収穫はどうなる?
イチゴの定植の時期が計画より遅れてしまった場合、生産者が最も直面する現実的な問題は「収穫開始の大幅な遅れ」です。農業現場の経験則としてよく語られるのが、「定植が1週間遅れると、収穫は10日〜2週間遅れる」という現象です。これは、植物の生育が単純なカレンダーの日数ではなく、「有効積算温度」によって制御されているためです。
参考)いちごの植付け遅れます – 森強の苺農園
秋口の1日と晩秋の1日では、イチゴが獲得できる熱量が全く異なります。9月下旬の平均気温が20℃前後であるのに対し、10月下旬には15℃以下に低下することも珍しくありません。定植直後の苗は、新しい土壌環境に適応し、新しい根(活着根)を伸ばすために多大なエネルギーと温度を必要とします。定植時期が遅れると、この活着プロセスが気温の低下期と重なってしまい、スムーズな活着が阻害されます。活着が数日遅れるだけで、その後の葉の展開速度(出葉速度)が鈍化し、結果として花芽の発達スピードも遅れるため、収穫開始の遅延幅が拡大してしまうのです。
参考)https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/enken/seika/yasai/ichigo/documents/r3yasai3_.pdf
さらに、収穫時期の遅れは「年内収量」の減少に直結します。イチゴ経営において、クリスマス需要や年末年始の贈答用需要が見込める12月の単価は非常に高く、この時期の収量を逃すことは経営的な損失が大きくなります。特に「さがほのか」や「紅ほっぺ」のような促成栽培品種では、年内の収量確保が作型上の重要課題です。定植が遅れることで、第一花房(頂果房)の収穫ピークが1月以降にずれ込むと、単価の下落時期と重なり、収益性が圧迫される可能性があります。
参考)https://www.semanticscholar.org/paper/349e6781184c7c5dd66bef4e4fa6aca47ff27e37
また、収穫の遅れは「株の連続性」にも影響を与えます。第一花房の収穫が遅れると、続く第二花房(脇花房)の出蕾や開花も玉突き事故のように遅れていきます。これにより、春先の収穫ピークである3月〜4月に収穫の谷間(中休み)が発生しやすくなり、労働配分の計画が狂う原因にもなります。したがって、定植が遅れた場合は、収穫開始が遅れることを前提とした出荷計画の修正や、後述するような温度管理による生育促進策が不可欠となります。
収穫遅れと年内収量への影響に関する参考情報。
定植時期がイチゴ‘さがほのか’の収量に及ぼす影響(論文データ)
イチゴの定植後の活着を促進する水管理のコツ
イチゴの定植が遅れてしまった場合、その遅れを取り戻すための最初にして最大のチャンスは「活着(カッチャク)」のスピードアップにあります。活着とは、苗場のポットから本圃(栽培ベッドや土壌)へ移植された苗が、新しい環境に根を伸ばし、自立して水分や養分を吸収できるようになる状態を指します。遅れて定植した苗を、いかに短期間でスムーズに活着させるかが、その後の生育スピードを決定づけます。ここで最も重要なのが「水管理」です。
参考)10月にイチゴの葉が大きくなる原因と対策【促成栽培】
定植直後の水管理における最大のポイントは、「活着までは絶対に土壌水分を切らさない」ことです。イチゴの根は乾燥に非常に弱く、特に移植直後の新しい白根(新根)は、土壌の隙間に存在する水分(毛管水)を求めて伸長します。定植が遅れて気温が下がってきている時期であっても、定植当日から数日間は、株元を中心にたっぷりと灌水を行う必要があります。これを「活着水」と呼びますが、単に水をやるだけでなく、苗の根鉢(ルートボール)と本圃の土壌を水で密着させるイメージで行うことが重要です。土と根の間に空隙があると、根はそこから乾いて枯死してしまいます。
具体的なテクニックとして、以下の手順が推奨されます。
- 定植前のドブ漬け: 定植する直前の苗(ポットの状態)を、殺菌剤や発根促進剤を希釈した水に浸漬(ドブ漬け)し、根鉢内部まで完全に吸水させておきます。これにより、定植直後の水分ストレスを最小限に抑えることができます。
- 定植直後の多量灌水: 定植直後は、畝や培地から水が滴り落ちる程度まで十分に灌水します。これは土壌中の物理構造を落ち着かせ、毛細管現象を回復させるためでもあります。
- 頻度重視の灌水: 一度に大量の水をやるよりも、土壌表面が乾きかけたらすぐに与える「少量多回数」の管理が理想的です。特に定植遅れの場合は地温が低くなりがちなので、冷たい水を大量に与えて地温を下げすぎるリスクを避けるためにも、日中の暖かい時間帯を選んでこまめに水を与える方が根の活動には有利です。
- 葉水(シリンジ)の活用: 晴天時は葉からの蒸散が激しく、根からの吸水が追いつかずに萎れることがあります。スプリンクラーや手散布で葉面に霧状の水をかける「葉水」を行うことで、葉の気孔を閉じさせすぎずに光合成を維持し、活着を助けることができます。
ただし、過剰な灌水による「湿害」には注意が必要です。排水性の悪い圃場や、粘土質の土壌で定植が遅れた場合、低温下で水が停滞すると酸素欠乏により根腐れを起こします。定植が遅れた時期は気温だけでなく地温も下がっているため、水の乾きが遅くなります。土壌の湿り具合を指で触って確認し、「湿っているが過湿ではない」状態をキープする繊細な観察眼が求められます。
イチゴの定植の遅れを挽回する追肥と温度管理
定植の遅れによる生育の遅延を物理的に取り戻すためには、植物の代謝を意図的に高める「積極的な管理」が必要になります。自然任せにしていては、遅れはそのまま収穫の遅れとして固定化してしまいます。ここで重要になるのが、「温度管理」と「肥料(追肥)」の組み合わせによるブースト効果です。
まず温度管理についてですが、定植が遅れた場合は、通常よりも「保温開始」のタイミングを早めることが有効です。通常、イチゴは一定期間の寒さに当てる(低温遭遇)ことも重要ですが、活着と初期生育を優先する場合は、ビニールハウスのサイド換気を早めに閉め、夜温を確保する戦略をとります。特に、日中のハウス内温度を通常よりやや高めの28℃〜30℃程度まで許容し、光合成を最大化させます。そして、夕方の閉め込み時間を早めて余熱をハウス内に閉じ込め、夜間の温度低下を緩やかにします。夜温を15℃〜18℃程度に保つ時間を長くすることで、呼吸による消耗を抑えつつ、根や葉の伸長に必要な代謝活動を維持させます。
参考)https://www.semanticscholar.org/paper/8500751c4c543ea3463d07cc4fae4d0d0f9d9a04
次に追肥戦略です。定植遅れの株は根量が不足しているため、根を育てる肥料成分である「リン酸」と、植物ホルモンの活性を高める資材を重点的に施用します。
特に有効なのが、吸収効率の高い「亜リン酸」系の液体肥料の葉面散布や灌注です。リン酸は通常、土壌中では移動しにくく根から吸収されにくい成分ですが、亜リン酸は植物体内への移行がスムーズで、根の伸長やクラウンの充実を強力に後押しします。
また、曇天が続く場合や気温が低い場合は、光合成能力が落ちているため、即効性のある「アミノ酸」や「糖(グルコースなど)」を含む液肥を葉面散布し、エネルギー源を直接補給することも効果的です。これにより、根からの吸収力が弱い状態でも、地上部の生育をサポートすることができます。
さらに、物理的な刺激として「わき芽(腋芽)かき」や「枯れ葉取り」を適度に行うことも重要です。不要な葉や弱い脇芽を取り除くことで、株の栄養を主芽(メインのクラウン)と展開中の新葉に集中させることができます。ただし、定植遅れの株は葉数自体が少ないことが多いため、健全な葉まで取りすぎて光合成量を落とさないよう、枯れた葉や病気の葉のみを除去する慎重な作業が求められます。
イチゴの定植を10月以降にする高温対策のメリット
ここまで「定植の遅れ=デメリット」という前提で対策を解説してきましたが、近年の農業現場、特に温暖化が進行する地域においては、あえて定植時期を10月以降に遅らせる「遅植え」が、生存戦略としてポジティブに採用されるケースが増えています。これは「高温対策」としての側面が非常に大きいです。
従来の栽培暦では9月中旬の定植がスタンダードでしたが、近年の9月は最高気温が30℃を超える真夏日が続くことが珍しくありません。イチゴは冷涼な気候を好む植物であり、地温が25℃を超えると根の機能が著しく低下し、呼吸過多による消耗が激しくなります。さらに深刻なのが、高温多湿環境を好む「炭疽病(たんそびょう)」や「萎黄病(いおうびょう)」といった致命的な土壌病害の蔓延です。これらの病原菌は25℃〜30℃で最も活発に増殖するため、無理に9月中旬に定植し、高温のストレスを受けた苗は、一気に病気に感染して枯死するリスクが高まります(立ち枯れ現象)。
あえて定植を10月に入ってから、あるいは最高気温が25℃を下回るようになるまで待つことには、以下のような明確なメリットがあります。
- 病害リスクの回避: 地温が低下してから定植することで、炭疽病菌などの活性を抑え、感染リスクを劇的に下げることができます。感染苗が混入していた場合でも、発病を抑制できる可能性が高まります。
- 活着の安定化: イチゴの根は地温20℃前後で最もよく伸長します。猛暑期の定植では高温障害で根が焼けることがありますが、涼しくなってからの定植であれば、根へのストレスが少なく、スムーズに活着します。
- 花芽分化の確実性: 花芽分化には低温と短日条件が必要です。9月の高温で花芽分化が遅れる(ボケる)現象が頻発していますが、遅植えにすることで、確実に花芽分化を確認してから(あるいは自然低温に十分に遭遇してから)定植することができ、定植後のツルボケ(過繁茂)を防ぐことができます。
もちろん、前述の通り収穫開始は遅れますが、「病気で株が全滅して植え替えになるコスト」や「欠株による収量減」と比較すれば、10日〜2週間程度の収穫遅れは許容範囲内であるという経営判断も成り立ちます。特に育苗設備を持たない購入苗農家にとっては、苗が到着してすぐに植えるのではなく、涼しい場所で数日間管理して温度を下げてから植えるといった工夫も有効です。
高温下での定植リスクと遅植えの判断に関する参考情報。
2025年9月における高温下でのイチゴ苗管理に関する考察と遅植えの推奨
イチゴの年内収量を落とさない花芽分化の重要性
定植の時期がいつであれ、イチゴの収量を決定づける最大の生理的イベントが「花芽分化(かがぶんか)」です。特に「定植が遅れた」場合、この花芽分化の状態を正確に把握せずに定植してしまうと、致命的な失敗につながる恐れがあります。
花芽分化とは、苗の成長点(クラウンの内部)が、葉を作ることから花を作ることへと切り替わるスイッチのことです。このスイッチが入っていない(未分化の)状態で定植を行い、さらに定植後の高温や多肥管理(窒素過多)によって栄養成長が促進されてしまうと、苗は「まだ体を大きくする時期だ」と勘違いし、いつまでたっても花がつかない、あるいはランナーばかりが出てくる「ツルボケ」状態になります。こうなると、年内の収穫は絶望的になり、最初の収穫が春先までずれ込むことさえあります。
参考)今年の自然花芽分化は異常気象で異常に早いため、定植時期が2週…
逆に、定植が遅れたからといって、花芽分化が進みすぎた(分化後日数が経過しすぎた)苗を植えるのも問題です。ポット内で根が回りきり、老化苗(根詰まり状態)になってから定植すると、活着が悪くなるだけでなく、株が十分に大きくならないまま開花・結実してしまいます。すると、果実を育てるための葉の枚数や根の量が足りず、極端に小さなイチゴしかできなかったり、収穫後に株が急激に弱ったりします(なり疲れ)。
定植が遅れる場合こそ、以下の手順で花芽分化の管理を徹底する必要があります。
- 検鏡(けんきょう)の実施: 地域の普及センターやJAに依頼し、顕微鏡で成長点を観察して、花芽分化が起きているかを確実にチェックします。未分化であれば、定植を待つか、短日夜冷処理などの人為的な処理が必要です。
- 窒素切りの調整: 花芽分化を促進するために育苗後半で肥料(窒素)を切りますが、定植が遅れることが確定している場合は、極端に肥料を切りすぎると苗が老化します。液肥で微量の窒素を補い、苗の若さを保ちつつ分化を待つという高度な管理が求められます。
- 定植後の温度管理との連動: 花芽分化が確認できた直後に定植する場合は、前述の通り、活着促進のためにやや高めの温度管理を行います。しかし、分化が不安定な(ボーダーラインの)場合は、定植直後に高温にしすぎると、分化しかけた花芽が消えて栄養成長に戻ってしまう「脱分化(破棄)」が起きるリスクがあります。このため、分化が確実になるまでは過度な高温を避け、換気を徹底するといった微調整が必要です。
「定植の遅れ」というハンデを背負っているからこそ、苗の生理状態(体内時計)を正確に読み取り、その状態に合わせたアクセルとブレーキの操作を行うことが、年内収量を確保する唯一の道となります。
花芽分化と定植のタイミングに関する参考情報。
窒素中断処理がイチゴ種子繁殖型品種‘よつぼし’の花成誘導に及ぼす影響

静岡県産 いちご(紅ほっぺ または きらぴ香)【2L~Mサイズ (20~30粒) 約250g×1トレー】冬いちご 苺 イチゴ 果物 フルーツ ギフト ストロベリー 業務用 ケーキ 【こだわりの果物屋 紅光】