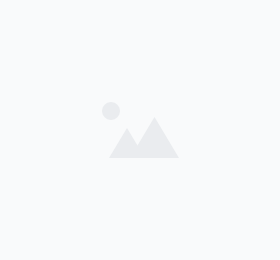イチゴの窒素中断と葉色
イチゴの窒素中断がもたらす葉色変化とC/N比の重要性
イチゴの育苗において、最も重要かつ繊細な管理の一つが「窒素中断」です。多くの生産者が経験的に行っているこの作業ですが、植物生理学的な視点からそのメカニズムを深く理解しているかどうかで、毎年の花芽分化の安定感に大きな差が生まれます。なぜ窒素を切ると葉色が変わり、花芽ができるのでしょうか。その鍵を握るのが「C/N比(炭素窒素比)」という概念です。
C/N比とは、植物体内の炭水化物(C)と窒素(N)のバランスを示す指標です。植物は基本的に、窒素成分が多い状態(C/N比が低い状態)では、葉や茎を大きくする「栄養成長」を優先します。一方で、窒素が減少し炭水化物の割合が高まる(C/N比が高い状態)と、子孫を残すための「生殖成長」、つまり花や実を作るモードへと切り替わります。イチゴの窒素中断は、人為的に窒素供給を絶つことでこのC/N比を急激に高め、強制的に花芽分化のスイッチを入れる作業なのです。
葉色が濃い緑色から淡い黄緑色へと変化するのは、単なる肥料切れのサインではありません。これは、植物が体内の窒素を再利用しようとする生存戦略の現れです。供給される窒素が途絶えると、イチゴは古い葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)を分解し、そこに含まれる窒素を成長点や新しい葉へと転流させようとします。葉緑素は植物が光合成を行うための緑色の色素ですが、その構成要素には窒素が不可欠です。窒素中断によって新しい窒素が入ってこなくなると、植物は既存の葉緑素を分解して窒素をリサイクルするため、結果として葉の緑色が抜け、黄色味を帯びてくるのです。
このプロセスが正常に進んでいるということは、イチゴの株内で「栄養成長から生殖成長への転換」がスムーズに行われている証拠です。しかし、単に肥料を切れば良いというものではありません。光合成による炭水化物(C)の蓄積も同時に必要だからです。もし、天候不順で日照が不足している場合、いくら窒素を切っても炭水化物が生成されず、C/N比は思うように高まりません。逆に、夜温が高すぎて呼吸による炭水化物の消費が激しい場合も同様です。「窒素中断=肥料を切る」という単純な図式ではなく、「体内の窒素濃度を下げつつ、光合成産物を蓄積させる」という動的なバランス調整こそが、窒素中断の本質であることを理解しておく必要があります。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10783531/
イチゴの窒素中断成功の鍵となる葉色と花芽分化の基準
窒素中断が順調に進んでいるかどうかを判断するために、生産現場で最も頼りにされるのが「葉色」の観察です。しかし、「色が抜ければよい」という大雑把な認識では、高品質な一番果を収穫することはできません。目指すべき「理想の葉色」とはどのようなものでしょうか。
一般的に、窒素中断を開始してから約2週間から3週間程度で、葉色の変化が顕著になります。理想的な状態は、株全体の葉色が均一に淡くなり、新葉(展開中の若い葉)の色が特に薄い黄緑色になることです。これを専門用語で「色が抜ける」と表現しますが、病的な黄色(クロロシス)とは異なります。生命力を感じさせる明るいライムグリーンが理想です。逆に、古い葉だけが極端に黄色くなり、新葉が濃い緑色のままである場合は要注意です。これは窒素の転流がうまくいっていないか、あるいは根に何らかの障害があり、窒素吸収と転流のバランスが崩れている可能性があります。
また、葉色だけでなく「葉柄(ようへい)」の色にも注目してください。窒素が十分に切れ、C/N比が高まってくると、葉柄が赤く色づく現象が見られます。これはアントシアニンという色素の蓄積によるもので、植物が一種のストレス状態にあることを示しています。イチゴにおけるこのストレスは、花芽分化を誘発するためのポジティブなシグナルとして捉えられます。葉の色が淡くなり、葉柄が鮮やかな赤色を呈していれば、花芽分化の準備が整った強力なサインです。
さらに、品種による葉色の違いも考慮する必要があります。「とちおとめ」や「紅ほっぺ」のように比較的葉色が抜けやすい品種もあれば、「あまおう」のように元々の葉色が濃く、窒素が抜けても見た目の変化がわかりにくい品種もあります。品種ごとの特性を把握せずに、「まだ色が濃いから」と過度な窒素切りを行うと、極度の肥料不足による「老化苗」を作ってしまうリスクがあります。老化苗は、定植後の活着が悪く、腋花房(二番果)の出現が遅れるなど、長期的な収量減につながります。
基準とすべきは、あくまで「その品種における健全な淡さ」です。可能であれば、葉色板(カラーチャート)を使用して、客観的な数値として葉色を記録することをお勧めします。例えば、窒素中断前はカラーチャート値で4〜5だったものが、花芽分化期には2〜3程度まで低下する推移を確認できれば、管理は成功していると言えます。感覚だけに頼らず、数値に基づいた基準を持つことが、安定生産への近道です。
イチゴの窒素中断で葉色が変化しない失敗原因と対策
「予定通りに肥料を切ったはずなのに、いつまでたっても葉色が濃いまま抜けない」。これは多くのイチゴ農家が直面する悩みであり、花芽分化の遅れに直結する深刻な問題です。なぜ、窒素中断を行っても葉色が変化しないのでしょうか。その原因は、主に土壌環境と気象条件の二つに分類されます。
一つ目の原因は「培地内の残留窒素」です。特に有機質肥料を主体とした育苗を行っている場合によく見られます。有機質肥料は微生物によって分解されて初めて植物が吸収できる無機態窒素に変わりますが、この分解速度は温度に依存します。夏場の高温期には微生物の活性が急激に高まり、想定以上のスピードで肥料分解が進んで、大量の窒素が放出されることがあります。これを「肥効の湧き出し」と呼びます。計算上は肥料切れの時期であっても、ポットの中で窒素が湧き出し続けていれば、当然葉色は抜けません。
対策としては、育苗後半には肥効調節が難しい有機肥料の使用を控え、コントロールしやすい液肥主体の管理に切り替えることが有効です。もし湧き出しが起きてしまった場合は、多めの潅水を行って鉢底から窒素成分を洗い流す「リーチング(脱塩)」を行うか、最終手段として断根を行い、物理的に吸収を遮断する方法があります。
二つ目の原因は「ポットの底からの根出し」です。育苗ポットを地面や防草シートの上に直接置いている場合、イチゴの根がポットの穴から飛び出し、地面の土壌に活着してしまうことがあります。地面に残っている前作の肥料分や、土壌本来の地力窒素を勝手に吸収してしまうと、いくらポット内の肥料を切っても窒素中断に繋がりません。
この対策としては、ポット上げ(スペーシング)を行い、根と地面の縁を切ることが基本です。また、育苗ベンチを使用したり、透水性のないシートを敷くなどして、物理的に根が地面に到達しない環境を作ることが重要です。
三つ目の原因として見落とされがちなのが「高温による呼吸消耗」です。これは葉色が抜けないというよりは、C/N比が上がらない原因です。夜温が高いと、イチゴは夜間も激しく呼吸を行い、昼間に光合成で作った炭水化物を消費してしまいます。窒素は切れていても、炭水化物(C)がたまらなければ相対的にNの比率が下がらず、花芽分化のスイッチが入りません。
この場合、葉色はやや淡くなっても花芽が来ないという現象が起きます。対策としては、夕方に打ち水をして気化熱で夜温を下げたり、日中の遮光を適切に行って葉温の上昇を防ぐことが求められます。特に近年の猛暑下では、窒素コントロール以上に温度コントロールが花芽分化の成否を分ける要因となっています。
イチゴの窒素中断後の追肥タイミングと育苗の仕上げ
窒素中断によって花芽分化が無事に確認されたら、次に行うべきは「窒素レベルの回復」です。いつまでも窒素飢餓状態にしておくと、形成された花芽の発育が悪くなり、貧弱な花しか咲かなくなります。また、定植後の発根力も低下し、初期生育でのつまずき原因となります。この窒素レベルを戻す作業を「葉色戻し(はいろもどし)」と呼びますが、そのタイミングは非常にシビアです。
ベストなタイミングは、「検鏡によって花芽分化が確実に確認された直後」です。具体的には、成長点が肥厚し始め、がく片形成期に入った段階が目安です。この段階まで進んでいれば、再び窒素を与えても栄養成長に戻る(花芽が葉芽に戻ってしまう「分化ボケ」を起こす)リスクは低くなります。
逆に、まだ分化が確定していない「分化始動期」や「肥厚初期」の段階で慌てて追肥をしてしまうと、植物は再び栄養成長モードに戻ろうとし、せっかく進みかけた花芽分化がキャンセルされてしまうことがあります。これが最も恐ろしい失敗パターンです。「そろそろ時期だから」とカレンダーの日付だけで追肥を再開するのではなく、必ず検鏡で発育ステージを確認してから肥料を与えることが鉄則です。
追肥の方法にも注意が必要です。飢餓状態にある根に、いきなり高濃度の肥料を与えると「肥料焼け」を起こし、根を傷めてしまいます。まずは薄い液肥(規定倍率の2倍〜3倍程度に薄めたもの)から開始し、徐々に濃度を上げていくのが安全です。葉面散布も有効な手段です。根からの吸収が弱っている場合でも、葉から直接アミノ酸や微量要素を吸収させることで、速やかに樹勢を回復させることができます。
定植の1週間〜10日前までには、葉色が「やや淡い緑色」から「健全な緑色」に戻りつつある状態を目指します。ただし、真っ黒になるほど窒素を効かせる必要はありません。定植直後は根が切れて吸水力が落ちるため、体内の窒素濃度が高すぎると蒸散量が多くなり、萎れやすくなるからです。
理想的な仕上げは、花芽分化を完了させつつ、定植後の発根に必要なエネルギー(炭水化物)と、初期生育をスタートさせるための最低限の窒素(アミノ酸)が体内にプールされている状態です。この絶妙なバランス着地点を見極めることこそが、プロの育苗技術の真骨頂と言えるでしょう。
イチゴの窒素中断は葉色より硝酸態窒素と検鏡を信じろ
ここまで「葉色」の重要性を説いてきましたが、最後に矛盾するようですが最も重要な真実をお伝えします。「葉色だけで窒素中断の成否を判断するのは危険である」ということです。
近年、多くの研究機関や先進的な農家で指摘されているのが、「葉色と植物体内の硝酸態窒素濃度には必ずしも正の相関がない場合がある」という事実です。
例えば、葉が分厚く硬い品種や、水分ストレスがかかって葉が萎縮気味の株では、葉緑素が凝縮されて見えるため、実際には窒素レベルが下がっているにもかかわらず、見た目は濃い緑色に見えることがあります。この場合、「まだ色が抜けない」と判断してさらに窒素を切り続けると、過度なストレスで株が衰弱し、チャノホコリダニなどの害虫被害やうどんこ病の蔓延を招く結果になります。
逆に、根腐れや微量要素欠乏(マグネシウム欠乏など)を起こしている株では、体内の硝酸態窒素濃度が高いままであっても、葉が黄色く変色することがあります。これを見て「窒素が抜けた!花芽分化は順調だ」と誤認して定植すると、実際には花芽が未分化のままであり、定植後にランナーばかりが出て花が咲かないという事態に陥ります。
このような「目視の罠」に陥らないために、プロの生産者が導入しているのが、小型反射式光度計や試験紙を用いた「葉柄中の硝酸態窒素濃度測定」です。葉柄の汁液を絞り、測定器にかけることで、リアルタイムの窒素栄養状態を数値(ppm)で把握できます。
一般的な目安として、花芽分化を誘導するためには、葉柄中の硝酸態窒素濃度を数100ppm以下(品種や測定法によるが、一般的には低レベル)まで下げる必要があるとされています。たとえ葉色が濃く見えても、数値が目標値を下回っていれば、自信を持って窒素中断を終了し、検鏡へと進むことができます。
最終的な確定診断は、やはり「検鏡(顕微鏡による成長点の観察)」に勝るものはありません。葉色はあくまで状況証拠に過ぎず、硝酸態窒素濃度は有力な証拠、そして検鏡こそが判決です。
「葉色は目安、数値は道標、検鏡は証明」。この3段構えのチェック体制を構築することこそが、異常気象が常態化する現代農業において、安定してイチゴを生産するための最強の対策となります。自分の目を過信せず、科学的なデータを味方につけて、今年の窒素中断を完璧なものにしてください。
参考)https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/509412.pdf
HTMLリンク。
農研機構:大規模いちご生産技術導入マニュアル(花芽分化技術の詳細な解説あり)
愛知県:イチゴ「愛経4号」の栽培指針(検鏡と花芽分化の具体的な日程データが参考になります)
福岡県農林業総合試験場:イチゴの葉柄中硝酸態窒素濃度に関する研究(数値管理の根拠となるデータ)
静岡県:紅ほっぺの理想的な定植苗とその育成法(葉色と体内窒素の関係性についての深い考察)

生食できる夏イチゴ 6月~11月発送 秋田県産 なつあかり 夏のしずく ご自宅用 ケーキやスイーツに 小粒サイズ (2トレー(500g))