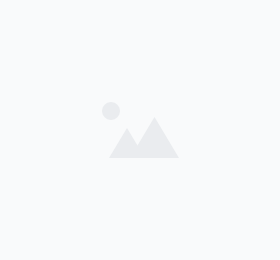イチゴの花芽戻り
イチゴの花芽戻りの症状と基礎知識
イチゴ栽培において、生産者を最も悩ませる生理障害の一つが「花芽戻り(はなめもどり)」です。これは、一度順調に花芽分化(かがぶんか)を開始したはずのイチゴの苗が、何らかのストレスや環境要因によって再び栄養成長(葉や茎を伸ばす成長)へと逆戻りしてしまう現象を指します。
通常、イチゴは秋の低温と短日条件を感じ取って、体内のスイッチを「葉を作るモード」から「花を作るモード」へと切り替えます。これを花芽分化と言います。しかし、花芽戻りが起きると、顕微鏡検査(検鏡)で一度は「分化開始」を確認できたにもかかわらず、その後花房が発達せずに退化したり、あるいは蕾(つぼみ)が奇形化して止まってしまったりします。
現場でよく見られる症状としては、定植後にいつまでたっても頂果房(一番最初の花房)が出蕾(しゅつらい)してこない、あるいは出てきた花房が貧弱で黒く枯死している、といったケースが挙げられます。最悪の場合、頂果房が完全に飛んでしまい、収穫開始が大幅に遅れることになります。これは年内の高単価な時期の出荷を逃すことを意味し、経営的なダメージは計り知れません。
花芽戻りは、単に「花が咲かない」だけでなく、株の生育リズムを大きく狂わせます。一度栄養成長に戻った株は、再び花芽を作るために必要な条件(低温・短日・低窒素)が揃うまで、ひたすら葉を展開し続けます。これを「つるぼけ」に近い状態と捉えることもできます。特に促成栽培においては、クリスマス需要に合わせた出荷計画が全て狂ってしまうため、この生理メカニズムを正しく理解しておくことが極めて重要です。
この現象は「分化」と「発達」のプロセスの違いを理解していないと見落としがちです。花芽分化は「スイッチが入ること」であり、その後の「花芽発達」はスイッチが入った後に実際に組織が形成されるプロセスです。花芽戻りは、この「発達」の初期段階で発生するトラブルなのです。
農林水産省の気候変動レポートでも、近年の温暖化による花芽分化の不安定さが指摘されています
農林水産省:野菜(いちご)の適応策レポート
イチゴの花芽戻りの原因は高温と窒素管理
イチゴの花芽戻りを引き起こす二大要因は、「高温」と「窒素過多」です。これらは単独で作用することもありますが、多くの場合、この二つが複合的に絡み合って発生します。
まず「高温」についてです。イチゴの花芽分化は一般的に平均気温が25℃以下になると誘導されやすくなります。しかし、近年問題になっているのは、分化が始まった直後の残暑です。一度花芽分化のスイッチが入っても、その直後に平均気温が25℃を超えるような高温、特に夜温が高い状態が続くと、植物体内のホルモンバランスが崩れ、再び栄養成長へのシグナルが優勢になってしまいます。
具体的には、定植直後のハウス内温度が高すぎることが原因となるケースが多いです。9月中旬から下旬にかけて、外気温は下がってきても、ハウス内は日射によって30℃、40℃に達することがあります。この時期に適切な遮光や換気を行わず、苗を蒸し風呂のような状態にしてしまうと、分化したばかりの幼い花芽は高温障害を受け、発育を停止して葉芽へと戻ってしまいます。
次に「窒素管理」です。植物は体内の窒素濃度が高いと、茎葉を大きくしようとする栄養成長が促進されます。逆に、窒素が切れかかってくると、子孫を残そうとして花や実をつける生殖成長へと移行します。これを「C/N比(炭素率)」で説明することがありますが、要は「窒素が効きすぎていると花ができにくい」ということです。
花芽戻りが起きるパターンとしてよくあるのが、花芽分化を確認してすぐに、慌てて定植し、すぐに規定量の元肥や追肥を効かせてしまう失敗です。まだ花芽が微細で不安定な時期に、根から大量の窒素が吸収されると、株は「今はまだ葉を茂らせる時期だ」と勘違いを起こします。これにより、せっかく始まった生殖成長のプロセスがキャンセルされ、花芽戻りが発生します。
- 高温リスク: 分化確認後も25℃以上の環境に置くこと。特に夜温の下がらない熱帯夜は危険。
- 窒素リスク: 分化直後の多肥、または元肥の効きすぎ。
- 複合リスク: 「高温」で代謝が上がり、肥料吸収が良くなった状態で「窒素」が過剰供給される最悪のパターン。
イチゴの生理障害についての詳細な解説はこちらが参考になります
AGRI JOURNAL:【イチゴ編】症状別で見る!生理障害・病害虫の原因と予防の基礎
イチゴの花芽戻りを防ぐ育苗と検鏡の失敗しないコツ
花芽戻りを防ぐための戦いは、本圃(ほんぽ)への定植前から始まっています。最も確実な対策は、育苗期における徹底した「窒素中断(窒素切り)」と、正確な「検鏡(けんきょう)」です。
窒素中断の徹底
育苗の後半、8月中旬以降は、意識的に苗への窒素供給を絶つ必要があります。これは単に肥料をやめるだけでなく、ポット内の残存肥料を消費させ、苗の色が淡い緑色(黄緑色に近い状態)になるまで持っていくことを意味します。「苗が痩せて見えて心配だ」といって最後まで液肥を与え続けると、体内の窒素レベルが下がらず、花芽分化が遅れるだけでなく、分化した後の「戻り」のリスクも高まります。
プロの農家は、葉柄(ようへい)の硝酸イオン濃度を測定するなどして、数値で管理することもありますが、基本は葉色を見て、しっかりと「肥料切れ」の状態を作ることが重要です。
検鏡の重要性と落とし穴
「カレンダーを見て9月20日だから定植しよう」というのは、失敗のもとです。その年の気候によって花芽分化の時期は平気で1週間〜10日前後します。必ず顕微鏡を使って、成長点が生長点肥大からガク片形成期に進んでいるかを確認してください。
ここで重要なのが、「検鏡のサンプル数」と「個体差」です。畑の端の苗を1株だけ見て「分化している」と判断するのは危険です。生育の平均的な株、やや遅れている株など、複数の株を検査し、全体の8割以上が分化していることを確認してから定植の判断を下すべきです。未分化の状態で定植し、ハウス内の高温多湿環境に置かれれば、その苗は確実に栄養成長へと爆走し、花芽はつきません。
育苗期の温度管理
夜冷育苗(やれいいくびょう)や短日処理などの設備がある場合は、それらをフル活用して確実に分化を誘導します。設備がない通常育苗の場合でも、育苗ハウスの風通しを良くし、夕方に打ち水をして気化熱で夜温を下げるなどの工夫が必要です。特に、近年は9月でも残暑が厳しいため、頭上潅水(ずじょうかんすい)による冷却効果もバカにできません。ただし、病気のリスクとのバランスを考える必要があります。
検鏡の技術的なポイントや窒素管理については、こちらの専門記事も参考になります
農業ざんまい:いちごの花芽分化条件と温度!検鏡での対策
イチゴの花芽戻りと定植後の肥料管理
無事に花芽分化を確認し、定植を行った後も気は抜けません。定植後の2週間は、花芽戻りが最も起こりやすい「魔の期間」とも言えます。ここでの肥料管理と水管理が、頂果房の運命を左右します。
「活着肥」の与えすぎに注意
定植後、苗を早く土に馴染ませたい(活着させたい)という親心から、すぐに高濃度の液肥を与えてしまう生産者がいますが、これは花芽戻りの直行便です。
活着には水が必要ですが、大量の窒素は不要です。定植直後は、根が傷んでおり吸収力も弱いため、まずは真水による灌水で根の伸長を促します。肥料を開始するのは、新しい白い根が動き出し、かつ頂果房の蕾が目視できる(あるいはクラウンの奥に確実に確認できる)状態になってからでも遅くありません。
初期肥料としては、窒素成分よりも、発根を促す微量要素やアミノ酸系の資材、あるいはリン酸主体の薄い液肥を使用するのが安全です。
定植直後の高温対策
定植後のハウスは、まだ葉が茂っておらず、地面(マルチや培地)からの反射熱で高温になりがちです。
- 遮光カーテン(寒冷紗)を日中閉める。
- 循環扇を回して空気を動かす。
- クラウン周辺を冷却するための局所的な散水。
これらの物理的な対策で、株周辺の温度を可能な限り下げます。特に、「花芽は熱に弱い」という意識を持ち、人間が暑いと感じる環境はイチゴにとっても過酷であることを忘れてはいけません。
水分ストレスの活用
過度な乾燥は禁物ですが、ダラダラと水を与え続けると徒長(とちょう)を招きます。メリハリのある水管理を行い、根に適度な酸素を供給することで、健全な生育を促します。水分過多もまた、栄養成長を助長する一因となります。
定植後の具体的な管理スケジュールや失敗例についてはこちら
ナレッジベース:イチゴの栽培管理ポイントと生理障害
イチゴの花芽戻りのリカバリーと品種選びの視点
万が一、花芽戻りが発生してしまった場合、どうすればよいのでしょうか。そして、そもそも花芽戻りしにくい品種はあるのでしょうか。ここでは、現場レベルでのリカバリー策と、品種選びという独自視点からの対策を提案します。
花芽戻り発生時のリカバリー
不幸にも頂果房が飛んでしまった(花芽戻りしてしまった)ことが確定した場合、焦って肥料を追加するのは逆効果です。まずは、「一番花は諦める」という冷徹な判断が必要です。
その上で、次に出てくる腋花房(えきかぼう:二番花)を確実に確保することに全力を注ぎます。具体的には、以下の手順を踏みます。
- 過繁茂した葉の整理: 栄養成長に戻った株は葉が巨大化し、脇芽(ランナー)も大量に出ます。これらをこまめに除去(葉かき・芽かき)し、株元に光を当て、風通しを良くします。物理的ストレスを与えることで、再度生殖成長への転換を促します。
- 温度を下げる: 遅れてでも花芽を入れるため、可能な限り低温管理を続けます。保温開始時期を通常より遅らせる勇気が必要です。
- ホルモン剤の慎重な利用: 専門的な指導員の助言が必要ですが、場合によってはジベレリンなどの植物ホルモン剤の使用を控え、逆に矮化剤(わいかざい)的な管理で徒長を抑えることも検討します(※農薬登録のある資材を確認すること)。
品種による感受性の違い
あまり語られませんが、花芽戻りのしやすさは品種によって大きく異なります。
- 早生品種(章姫、かおり野など): 花芽分化の感受性が高く、比較的戻りにくい傾向がありますが、一度戻ると草勢が強くなりすぎて制御が難しくなることがあります。
- 晩生品種・高冷地向け品種: 低温要求量が多いため、平暖地での早期定植では花芽戻り(または分化遅延)のリスクが高まります。
自分の栽培地域の気候と、作付けしようとしている品種の「花芽分化特性(限界日長や必要低温量)」の相性を再確認してください。「近所の人が植えているから」ではなく、「自分のハウスの環境(特に9月の温度)に耐えられる品種か」という視点で選定することも、立派な技術対策です。
最後に、花芽戻りは「起きてから対処する」ものではなく、「起きないように予防する」ものです。しかし、起きてしまった場合のダメージコントロールを知っているかどうかが、プロとしての腕の見せ所でもあります。一つの失敗でシーズンを投げ出さず、二番花以降でリカバリーして、トータルの収益を確保する粘り強い管理を心がけてください。
品種ごとの花芽分化特性の違いについての研究データはこちら
イチゴの四季成り性品種間における花芽分化の限界日長の差異(PDF)

【冷蔵】超大粒 いちご 約1,150g 糖度:11度以上 とちおとめ等 旬の品種をセンサー選別 ギフト お祝い イチゴ 苺 Stroberry 【菊池農園等】